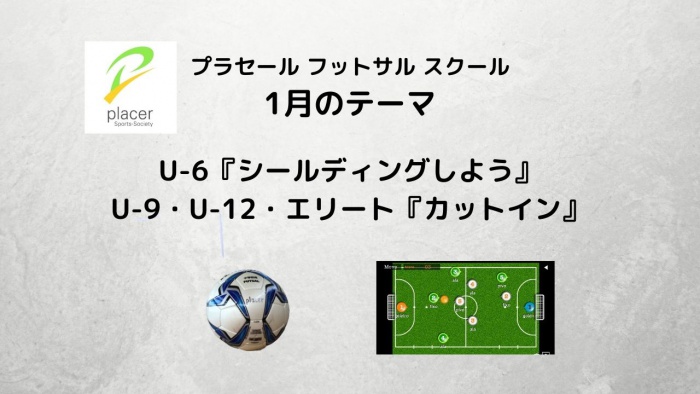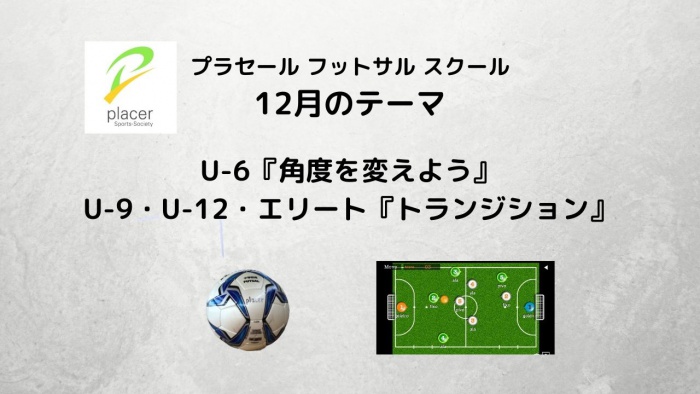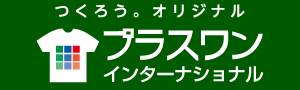ボール遊び教室 早期体験キャンペーン
火曜日にボール遊び教室を開催しています。ボール遊び教室はフットサルやサッカーに拘らず、運動能力の向上を目的としています。その名の通り「遊び」の中で身体を動かし、色々なボールを使って「投げる」「受ける」「蹴る」「止める」「よける」など様々な動きを身につけていきます。プレゴールデンエイジに向けてとても重要な要素です。また、新設翌月から定員数を満たすなど、とても人気のカテゴリーです。
このボール遊び教室限定の体験キャンペーンを実施します。
ボール遊び教室限定 早期体験キャンペーン
【対象】
次年度3歳児~年少になるお子様(現2歳児~3歳児)
【内容】
現在のボール遊び教室に無料体験参加できます。
※次年度の定員数を満たした場合はキャンセル待ちとなります。
【特典】3月までにご入会いただく場合
① 次年度を待たずにご入会いただけます
② 名前入りオリジナルプラクティスシャツをプレゼントします
※お渡しは入会月の翌月末頃となります
③ 3月までにご入会いただいた場合は4月の月会費を無料にします
ボール遊び教室の動画です。
プラセール・フットサル・スクールでは各曜日の通常クラスに無料で体験参加をしていただけます。各クラス定員数を設定しておりますので、ぜひお早めにお申し込みください。
フットサルがサッカーに有効だという記事をまとめています。ぜひ参考にされてください。
フットサルの価値
2022年1月のテーマ
1月のテーマです。
U-6クラス ≪シールディングしよう≫
横にいる相手に対して遠い足を使ったり、ターンの際に相手とボールの間に体を入れることをシールディングと呼んでいます。今月はシールディングを使った突破のテクニックを練習します。スピードに自信がない選手でも突破できるテクニックです。
U-9・U-12・エリートクラス ≪カットイン≫
アラ(サイド)での1対1で相手の内側へ切り込んで抜く攻撃技術です。フットサルでは利き足とは逆サイドに選手を配置することはベースですが、近年のサッカーでも利き足とは逆サイドのポジションに配置されることが増えてきました。これはボールの持ち方が後ろ足になることにより、視野が広がったり、縦突破がしやすくなったり、カットインして利き足でフィニッシュできたり、局面で最後の最後の瞬間までパスかドリブルかを選択できるメリットがあります。
最近のサッカー日本代表で言うと、久保建英選手や堂安律選手、カットインを見せながら縦突破を得意としている三苫薫選手などが利き足とは逆サイドに配置されています。Fリーグで活躍している選手の中にもカットインを得意としている選手が多数います。
冬休みまるまる体験でチームに所属している選手が多数参加してくれています。チーム所属選手にとっては間違いなくプレーの幅が広がるトレーニングになると思います。
現在2つのキャンペーンを実施中です。
6年生限定入会キャンペーン ⇒ 詳細はこちら
冬休みまるまる体験キャンペーン ⇒ 詳細はこちら
プラセール・フットサル・スクールでは各曜日の通常クラスに無料で体験参加をしていただけます。各クラス定員数を設定しておりますので、ぜひお早めにお申し込みください。
フットサルがサッカーに有効だという記事をまとめています。ぜひ参考にされてください。
フットサルの価値
第14回ちゅうぎんカップ香川少年フットサル大会 U-11
ご縁をいただいて指導させていただいているチームを引率して、第14回ちゅうぎんカップ香川少年フットサル大会 U-11に出場しました。会場はJフット丸亀。僕がフットサルを始めた20年以上前から個人的にもお世話になっており、ジュニア世代からのフットサルの普及にご尽力いただいている施設です。
会場ではスクール生にもたくさん会えて、クリニックでご縁をいただいた選手たちにもたくさん会えました。選手たちの方から寄ってきて声をかけてくれて、とても嬉しかったです。一人一人のプレーやスクール生対決なども観戦させていただきました。またスクール時にフィードバックさせていただきます。
ジュニアのフットサルでは競技規則でゴールクリアランスに制限があります。これは以前のバーモントカップで相手ゴール前にロングボールを入れて空中戦をさせるプレーが散見され、育成に繋がらないと判断されたためです。これによってGKからのボールはノーバウンドでハーフラインを超えられなくなりました。
このルール改正はとても有意義だと思っています。ゴールクリアランスを大きく投げられないので、守備側チームは前線からプレスにいきます。トランジションの早さ、マークのポジショニング、予測、インターセプト、チャレンジ&カバー、あらゆる守備のスキルを上げる経験を積むことができます。
一方、攻撃側チームはプレス回避が必要になります。オフザボールの動き、パスの受け方、ボールの持ち方、技術、プレーの優先順位、判断、グループプレー、あらゆる攻撃のスキルを上げる経験を積むことができます。
今大会でも連動して前線からプレスに行っているチームがいくつかありました。前線でボールを奪ってシュートで終わる。シュートが外れても、早く切り替えてまた前線でボールを奪う準備をする。試合時間の殆どを相手陣地でプレーできるようになるので強いです。
一方、そのプレスに対して、個の能力やロングボールでなくグループプレーで打開しようとしているチームもありました。ミスやエラーがあっても修正してチャレンジしていました。今うまくいかなくても、素晴らしい選手に成長していくと思います。
フットサルはボールに触る機会が多く、常にゴール前の攻防なのでプレーに責任が生まれ、サッカーの面白さと必要な技術や判断、グループプレーなどが凝縮されています。決勝大会も楽しみにしています。
会場では指導者の方々にもたくさん声をかけていただきました。本当にありがとうございます。指導者様のと繋がりは財産です。自チームの選手だけでなく、対戦相手の選手にも試合中に「ナイスプレー!」と声をかけられたり、試合後に話しかけたりされている素晴らしい指導者もおられます。みんなでいい選手を育てていければ最高です。
written by gonda
2021年11月度ゲームデイ
11月のテーマは『2人組からの展開』でした。
主にボール保持者の背後を周るアクションで
オーバーラップ、スイッチ
この2つのユニット戦術をお伝えしましたが2人の関係性なので相手に伝えることが重要だと
スクール中はコーチングする中で多くの選手がチャレンジし成功、失敗をする中でクオリティもなかなかに高くなった印象です。
さて、それでは優勝チームの発表です。
月曜日 U-9クラス
『キャベツ』
月曜日 U-12クラス
『緑のタヌキ』
火曜日 U-9クラス
『キャプテン翼』
火曜日 U-12クラス
『バナナ』
水曜日 U-9クラス
『ブラックファイヤー』
水曜日 U-12クラス
『サボテンバナナパイナポー』
木曜日 U-9クラス
『サッカー三昧』
木曜日 U-12クラス
『ほうれんそう』
木曜日 エリートクラス
『バナナ』
金曜日 U-9クラス
『マスカット』
金曜日 U-12クラス
『赤ずきん』
全カテゴリー キャプテン賞
今月のプラセール賞は2名。
つばさ選手
所属クラスの中でもコーチたちの言ったことがすぐに実践できるまさにお手本な選手です。
特にゲームデイでは勝利も優先しながら全ての味方の選手にゴールをお膳立てしたり普段のトレーニングの中でも他の選手に教えてあげたり素晴らしくコーチたちはあまり言わなくても上達しています。
ぎんじ選手
クラスに加入してそこまで月日は経っていませんが早くもプラセール賞をゲットしました。
スクール以外でも努力をしているのでしょう。みるみるとボールを扱う技術や、その時のテーマやテクニックを実践しようとする勇気。
ぜひとも継続して欲しいですね。
おめでとうございます!!
来月はU-6が『角度を変えよう』U-9以上が『トランジション』です。
トランジションとは切り替えのことです。
守備から攻撃。攻撃から守備。
この移行を行う作業において大切な要素がたくさんあります。
弊クラブのトップチームでも口酸っぱくこの切り替えは言ってますし
勝利に直結する非常に重要なテーマです。
是非お楽しみに。
2021年12月のテーマ
12月のテーマです。
U-6クラス
ドリブル中に角度を変えるテクニックを練習します。プロの実際の試合でもよく使われているテクニックです。股関節を動かし、キックの上達にもつながります。
U-9・U-12・エリートクラス
フットサルやサッカーの勝敗を大きく左右するトランジションのトレーニングです。ポジティブトランジションとネガティブトランジションがあり、細分化するとそれぞれに数的有利、数的同数、数的不利な状況があります。この中でポジティブトランジションに注力してトレーニングします。
現在2つのキャンペーンを実施中です。
6年生限定入会キャンペーン ⇒ 詳細はこちら
冬休みまるまる体験キャンペーン ⇒ 詳細はこちら
プラセール・フットサル・スクールでは各曜日の通常クラスに無料で体験参加をしていただけます。各クラス定員数を設定しておりますので、ぜひお早めにお申し込みください。
フットサルがサッカーに有効だという記事をまとめています。参考にされてください。
フットサルの価値