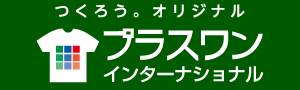第32回香川県少年サッカー選手権
通称「マルナカカップ」
6年生が目標の一つとしている大会です。
トーナメント戦なので負ければ敗退。リーグ戦とは違うモチベーションと雰囲気があります。昨今ジュニア世代にトーナメントは必要ないのではないかという話を耳にします。これは2022年に全日本柔道連盟が改革に踏み切ったことが他のスポーツ界にも一石を投じる形になっています。
JFAのHPでも関連記事が掲載されています。
小学生に全国大会は必要か
記事の主旨には大賛成です。ただ、リーグがしっかり確立されていることと、全ての選手に十分な出場機会があれば、トーナメントは有意義なものだと感じています。実際に今回のマルナカカップでも、選手たちのプレーからリーグ戦とは違う緊張感と想いを感じました。そういう経験ができるのはメリットだと思います。
マルナカカップは二回戦が終わって、現在16チームが勝ち上がっています。とても残念なのは出場機会を与えられない選手がいることです。試合を観た限りでは半分以上のチームに試合に出場していない選手がいました。ベンチにさえ入れてもらえずに保護者様と一緒にチームメイトを応援している6年生の選手もいました。
試合は今まで積み重ねてきたことの試し合いの場です。試合に出せない選手がいるのならば、それは選手の問題ではないと考えます。今日は大事な試合だから・・と仰る保護者様もおられますが、全ての試合が選手が成長する大事な試合です。
主役は選手で、試合は選手が成長する最大の機会です。その機会を大人が奪ってしまうのは本末転倒です。指導者とは選手たちに夢を与え、子どもたちの笑顔を作り、勝利を目指しながら、サッカーを通じて大切なことを伝え、豊かな人間に指し導いていく存在だと考えています。僕自身は未熟で不勉強なので、まだまだ努力が必要です。
小学生は育成年代です。勝利を目指す中で子どもたちの成長が大切です。今の結果よりも、次に対戦する時の結果の方が価値があると思います。
別会場だったり同時刻開催もあったので、フルでは観られない試合もありましたが、スクール生が所属している全てのチームの試合を観戦しました。スクール生が懸命にプレーしている姿を見るのはとても嬉しいです。また、たくさんの選手や保護者様から声をかけていただいて、とてもありがたかったです。
ご縁をいただいている全ての選手がサッカーを楽しめるように、そしてそれぞれのストロングポイントを伸ばしてチームで活躍できる選手になるように、全力を尽くします。
明日はガールズサマーカップでのスクール生たちの活躍を観戦に行きます。
高松校開校から1ヵ月
【高松校 開校から1ヵ月】出会いに感謝。そしてこれからの歩み。
4月に実施した無料体験会を経て、5月に新しくスタートした**高松校(あなぶきアリーナ香川)**は、おかげさまで1ヵ月が経とうとしています。体験やご入会をいただいた皆さま、本当にありがとうございます。
まだご入会に至っていない選手や保護者の皆さまとも、県リーグの試合会場やトレセンなど、さまざまな場面でお会いする機会がありました。まだ短い期間ではありますが、たくさんのご縁をいただけたことをとても嬉しく思っております。
正直に申し上げると、認知度の面で力不足を痛感しています。それでも、今の人数だからこそ一人ひとりとじっくり向き合うことができ、「この選手を必ず楽しませ、そして上達させたい」という想いは、日に日に強くなっています。
実際に通ってくれている選手たちは、毎回のスクールを笑顔で終え、着実に成長しています。一人ひとりと対話しながら、その選手の「ストロング(強み)」を伸ばし、自信につなげていく──そんな積み重ねが、やがて大きな成果へとつながると信じています。
【 高松校スケジュール(あなぶきアリーナ香川)】
U-9クラス(小学1〜3年生) 17:30〜18:30
U-12クラス(小学4〜6年生) 19:00〜20:10
基本は水曜日開催ですが、体育館の都合により月曜日や金曜日開催となる場合がございます。
現在は月会費制ではなくチケット制となっておりますので、ご都合に合わせて通っていただけます。
高松校は交通アクセスも良好で、自転車や電車で通うスクール生も多数いらっしゃいます。
【牟礼校は開校9年目】信頼のスクールへ
一方で、今年で**開校9年目を迎える牟礼校(牟礼総合体育館)**には、多くの選手たちが通ってくれています。
その特徴は何といっても、**新規入会のほぼすべてが「既存スクール生の紹介」**であること。これは、実際に通ってくださっている保護者様や選手たちが、プラセールを信頼し、周囲の方にすすめてくださっている証だと感じています。
また、チームに所属している選手においては、
「最近うまくなったね」「プレーに自信が出てきたね」
そんな周囲の声が、自然と私たちのスクールを広げてくれています。
ただし、特に高学年クラスについては、毎年すぐに満員となる傾向があり、今年度もU-12クラスは既に満員となっております。現在、多くの方にキャンセル待ちでお待ちいただいている状況です。
「高学年になってから」と思ってくださっている方も多いかもしれませんが、低学年からスタートすることで基礎を積み上げ、確かな成長へとつなげていくことができます。
【牟礼校スケジュール(牟礼総合体育館)】
■ 火曜日
ファーストステップクラス(年長〜小学2年生) 16:30〜17:20
U-10クラス(小学1〜4年生) 17:30〜18:30 ※残り1枠
U-12クラス(小学4~6年生) 18:40〜19:50 ※満員御礼
■ 木曜日
ファーストステップクラス(年長〜小学2年生) 15:40〜16:30
U-10クラス(小学1〜4年生) 16:40〜17:40
U-12クラス(小学4~6年生) 17:50〜19:00 ※満員御礼
エリートクラス(小学4~6年生・選考あり) 19:10〜20:20
プラセールのミッションはすべての子どもたちに“プレーする喜び”と“成長する実感”を届けること
「サッカーやフットサルを、もっと楽しんでほしい」
「試合で活躍できる自信をつけてほしい」
「人としても成長してほしい」
そんな願いをお持ちの保護者様に、ぜひ一度、私たちのスクールの雰囲気を感じていただけたらと思います。まずはお気軽に無料体験へお越しください。お子さまにとって、「楽しい」が「自信」につながり、「個の強み」と「チームで輝く力」を育む場を、私たちはご用意しています。
今後とも、プラセールフットサルスクールをよろしくお願いいたします!
高松校・牟礼校ともに、信頼と実績を積み上げ、地域に根差したスクールを目指してまいります。
観音寺校
プラセールフットサルスクールは牟礼校・琴平校・観音寺校の3ヵ所でスクールを開催させていただいています。その中の金曜日にすぽっシュTOYOHAMA(観音寺市豊浜町)で開催している観音寺校について書かせていただきます。
観音寺校にはチーム所属選手が一人もいません。全国でもチーム所属選手がいないスクールはとても珍しいのではないかと思います。それでもU-10クラスが定員間近、U-12クラスが満員と多くのお子様にご利用いただいています。
観音寺校のお子様は純粋で素直なお子様ばかりです。大人しい子、明るい子、優しい子、ガキ大将タイプの子、などなど色々な性格のお子様がいます。性格は違ってもどのお子様も純粋でリアクションがストレートに返ってきます。子どもなので間違った言動をしてしまうことはあります。その時に向き合って話すと、表情も返ってくる言葉も素直な心が表れています。
全員がチームに入っていない分、生活の中でフットサルやサッカーをプレーする機会が少ないです。そういうこともあって毎月最終週に行っているゲームデイに対するモチベーションがとても高いです。とても楽しみにしてくれていると同時に、優勝できなかった際に涙が出る子が複数います。悔しいと感じる気持ちは素晴らしいことです。しかし、優勝チームを発表した際に、優勝できなかった悔しさのあまり拍手をしないお子様が数名いることが気になっていました。
ある月のゲームデイを始める前に、グッドルーザーの話をしました。
誰もが優勝したいと思っている事。チームのために自分のストロングを発揮すること。ポジティブな声を出し続けること。味方のミスをカバーすること。それでも優勝できなかったとしても、勝者を讃えること。そして今回は負けたけど次は負けないぞという気持ちを持って、次の練習からも頑張ること。
グッドルーザーの話をしたその日から表情に悔しさを滲ませながらも勝者を讃えるようになりました。それだけなく、次のゲームデイにかける強い想いを翌週の練習から感じるようになりました。そりゃ上手くなります。
観音寺校はチーム所属選手が一人もいない分、当然のように他校と比べると全体のレベルは低いです。しかし全てのお子様が純粋で素直なので、1回のトレーニングでの吸収力が凄まじく、他校よりダントツで早いスピードで上達していきます。新年度から半年経った今は、どの学年にも今チームに所属したとすれば、間違いなく主力級に活躍できると断言できる選手が複数います。
トレーニングの流れとして、最初はアップも兼ねてボールフィーリングのメニューから入ります。簡単なものであっても雑にすることはなく、伝えているポイントを意識して全力で取り組みます。なので基礎のボールコントロールはとても上手です。他校のチーム所属選手でも顔を上げてボールフィーリングをするということがなかなか難しい選手もいますが、金曜日のスクール生は最初から当たり前のようにチャレンジし続けているので、何の問題もなく顔を上げてボールフィーリングをするお子様がたくさんいます。
テーマに対するトレーニングでは最初にミーティングでトレーニングの目的と説明をします。実際にトレーニングを進めながら、起こる現象に対してポイントをコーチングして修正していきます。どの曜日もまずはシンクロでコーチングします。フリーズで良いプレーを共有したり、改善します。なかなか改善できない場合はミーティングをします。金曜日のスクール生たちはできるできないに関わらず、シンクロで伝えられたポイントを意識して取り組むので、フリーズすることはあっても、ミーティングをすることがまずありません。最初と比べると明らかに改善します。そして最後のゲームの時間も長くなります。ゲームでもトレーニングしたことにチャレンジするので、毎回充実したトレーニングになります。
今年度の6年生たちが進学する中学にはサッカー部がないそうです。でもサッカーをやりたいのでクラブチームに行くことを検討しています。「サッカーを続けたい」と思ってくれることは当スクールの理念でもあるので、とても嬉しいことです。
当スクールでは全ての6年生に進学後のサッカーについてアンケートをとっています。他の部活に入ることを希望している選手もいますが、部活やクラブチームに入ることを検討している選手にはヒアリングをします。そしてクラブチームを希望する選手にはできる限りサポートをしています。
観音寺校の6年生がクラブチームを希望されているので、情報を収集して、いくつかのクラブチームに連絡させていただきました。お返事をいただけたチームに練習参加させていただくことになりそうです。
実戦経験がないという点は大きなディスアドバンテージです。練習会やもし入団したとしたら、適応するまでは苦労すると思います。それにしては基礎スキルはしっかりしているし個人戦術を持っています。何より彼らの姿勢ならサッカーを楽しみながら成長してくれるはずです。
話が少し逸れましたが、観音寺校のお子様は純粋で素直なお子様ばかりです。全員のリアクションがストレートという点は独特かもしれません。スクールの雰囲気もとてもいいです。なので、全員がフットサルを楽しみながらどんどん上達しています。
どの曜日のどのクラスもポジティブな雰囲気でフットサルを楽しんでいます。その中でも曜日やクラスによってそれぞれ特長があります。また機会を作って紹介していければと思います。
全日本女子フットサル選手権大会 全国大会
今季途中から監督を任せていただいたRiz Ferで全国大会に出場してきました。
全国大会は16チームによるトーナメントです。
日本女子フットサルリーグ上位4チーム
9地域サッカー協会から各1チーム
開催地都道府県サッカー協会から1チーム
前回大会予選参加チーム数上位2地域から各1チーム
まさに日本一のチームを決める大会です。
チームの監督をさせていただく前にチームクリニックを何度かさせていただいていました。
当時の選手たちはフットサルの知識はゼロに近い状態でした。
また、リーグは1勝1敗1分の4位で、試合映像を観ると戦い方や試合運びがとてももったいない状況でした。
しかし全ての選手のフットサルを上手くなりたいという姿勢に素晴らしいものがあり、ポジション別の能力が高い選手が複数いました。
確実に強いチームになる
そう感じました。
そのために
フットサルIQを上げていくこと
全国大会の経験をすること
この2点が必要だと考えました。
チームの目標として《全国を驚かせること》を設定しました。
つまり全国大会出場は最低限、さらにストロングを磨き続けることを設定しました。
これは選手たちへのコミットでもあり、自分へのコミットでもありました。
普段のトレーニングでフットサルの基礎をトレーニングしていきました。
ボールの持ち方、抜け方、2人組、ジョガーダ、数的不均衡、トランジション
選手たちの吸収力が凄まじく、驚くくらい早いスピードで変化してくれました。
全国大会に出場するためには勝利することが必要です。
しかしフットサルをしようとすると勝利が難しくなる時期があります。
勝利に導くために、今までの雰囲気を一新して《熱くポジティブに戦う》ことを共有しました。
そして、リアクションにならずストロングポイントで勝負することを求め続けました。
監督を引き受けてから、リーグは1敗のみ。
全てのゲームで前半の課題を後半で改善してくれました。
これはチームのストロングポイントになった部分だと思います。
それでも首位に勝点1差で2位となり、全国大会出場まではあと一歩届きませんでした。
リーグで優勝できなかった分、選手権への強い想いを共有できたと思います。
監督就任直後に開催された県大会では勝つためのプロセスを選手と一緒に構築しながら優勝できました。
リーグで経験を積み重ね、四国大会ではリーグで唯一敗れた相手に対してもしっかりと準備をしたことで勝利し、全国大会への切符を手にすることができました。
約半年間で今年度初めのチームとは全く違うチームになったと思います。
話は戻って全国大会。
抽選の結果、初戦の相手はアルコ神戸に決まりました。
前回準優勝
全日本女子フットサルリーグ所属
過去にこの大会で5回優勝
世界大会優勝経験もあり
日本代表・代表候補が複数在籍
今大会間違いなく優勝候補のチームです。
明らかに格上の相手に対してどう戦うか。
熱くポジティブに戦う
ストロングポイントで勝負する
相手をリスペクトしすぎて自分たちのストロングを見失っては本末転倒です。
受け身になってどうにかなる相手ではありません。
むしろトップレベルに自分たちの力がどこまで通用するかを試せる絶好の機会です。
全国大会で必要なことはチームと選手たちが持っている力を発揮できる状態にすることでした。
会場の雰囲気や相手にのまれないように、また浮かれてしまわないように、事前に必要な情報を共有しました。
多くの方に支えられてプレーできていること、四国代表であること、今まで戦ってきたチームや選手の想いを背負っていることも確認しました。
また、過去の自分の経験を還元して、できるだけ普段のコンディションで戦えるよう環境を整えようとしました。
アルコ神戸のファーストセットは日本代表セットでした。
事前に試合映像を分析していましたが、個のレベルも高く、フットサルの質も高く、トランジションもとても早い、まさに日本トップレベルでした。
しかし一つだけ勝機を見出していました。
ゲームのファーストシュートはこちらの2人組から崩したシュートでした。
ゴールまであと一歩でしたがGPに止められました。
それだけでなく、立ち上がりから数分間は相手陣地でプレーする時間が長く、ハイプレスは相手に脅威を与えていたと思います。
小さな勝機を選手たちはピッチでしっかり表現してくれていました。
日本代表セット相手に、いけるかもと感じられるほどイケイケでした。
選手たちは終始熱くポジティブに戦い、トランジションもとても早く、個々の全てを出してくれました。
気持ちも入っていて、失点を重ねても気持ちが切れることなく戦い続けてくれました。
全国を驚かせるという目標はほんの少し達成できたかもしれません。
しかしあらゆる面で相手の方が上でした。
トレーニングしてきた形をそのままやられて、お手本のような質の高さを見せてもらいました。
全国大会ではいつも感じてきた「決めきる力」の差を改めて強く感じました。
試合後には観戦されていた女子フットサル日本代表監督に声をかけていただきました。
男子の全国大会で過去に2回対戦した監督さんで、当時の話も含めて色々とお話をしたり聞かせていただきました。
全国の経験をするという設定は達成できました。
通用しなかったことが殆どでしたが、通用した部分や戦えた部分もありました。
選手たちは短期間で本当に成長してくれたと思います。
もう一度全国の舞台に立たせてくれた選手たちに感謝し、彼女たちを誇りに思います。
ここからがスタートです。
この経験が基準です。
2年目はリーグと選手権の2冠を達成します。
全日本女子フットサル選手権大会 四国大会
当スクールのスクールマスターである権田が監督を務めている『Riz・Fer(リズ・フェール)』が1月28日(日)にとくぎんトモニアリーナ(徳島県)で開催された全日本女子フットサル選手権大会四国大会に香川県代表として出場しました。
優勝を目指していた四国リーグは勝点1差で2位で終わり、全日本女子フットサル選手権にかける想いは一入でした。権田コーチとしては全国の舞台をプラセールや香川県選抜などで数回経験しており、なんとしてでもあの震えるような全国の舞台の経験を選手たちに経験してほしいという想いを強く持っていました。
準決勝の相手は松山城北FCLBさんでした。僕が監督を任せていただいてから7試合で敗戦は1試合だけなのですが、その唯一負けた相手で、チームとしては今季2戦2敗、突出した個を持っている選手がいるチームです。決勝のことは考えず、この準決勝に120%出し切ることが必要でした。
過去の対戦時の試合全体の流れと、得点シーンと失点シーンを分析して、どういうゲームプランで戦うのかを共有して臨みました。選手たちはゲームプランを理解したうえでアグレッシブに戦ってくれました。攻撃面は思い描いていたのとは程遠い内容でしたが、コンセプトとして共有している "熱く" "ポジティブに"戦うということをベンチも含めて全員で貫いてくれて、リスタート時のプレー原則のところを完璧に実践してくれて、なんとか勝利することができました。
もう一方の準決勝で四国リーグ上位リーグのチームを破って勝ち上がってきたJOGADAさんが決勝戦の対戦相手となりました。リーグを進めるにつれて明らかにフットサルの質が上がっているチームです。そのうえ気を付けるべき個の能力が高い選手が複数いるチームです。個人的には生では初見の対戦相手だったので、相手どうこうではなく自分たちのストロングポイントを発揮することに注力して臨みました。
普段のリーグは20分プレイングタイムの前後半です。今大会はそれを2試合やります。ある意味男子より過酷な状況です。体力面をどうマネジメントするかは重要なポイントとして考えていましたが、選手たちは気持ちで体力の部分をカバーしてくれました。
しかしこういう一発勝負のゲームでは一瞬の気の緩みがゲームの流れと結果を左右します。それをコントロールすることにパワーを使うことが多い、とても疲れる試合となりました。実際に前半は3-0でリードしていましたが、後半途中で4-3まで追いつかれました。
全体のマネジメントは即断ができず監督として反省点が多かったのですが、このゲームは個の能力に助けられたゲームとなりました。結果6-4で勝利。四国代表として全国大会へ進出する権利を獲得しました。
今年度当初のリズの四国リーグの映像を観た時、正直、ただのミニサッカーでとてももったいないと感じました。そこから考えると明らかに違うチームに成長しました。彼女たちのひたむきな姿勢と努力は尊敬に値します。
全国大会は2/10-2/12に栃木県で開催されます。全16チームによる負ければ終わりのトーナメントです。
全てのチームが格上ですが、まず初戦を勝ちにいきます。
まだまだ色んな意味でとても若いチームです。全国レベルを経験することで、大きなステップアップをすることは間違いありません。ぜひ注目していただければと思います。